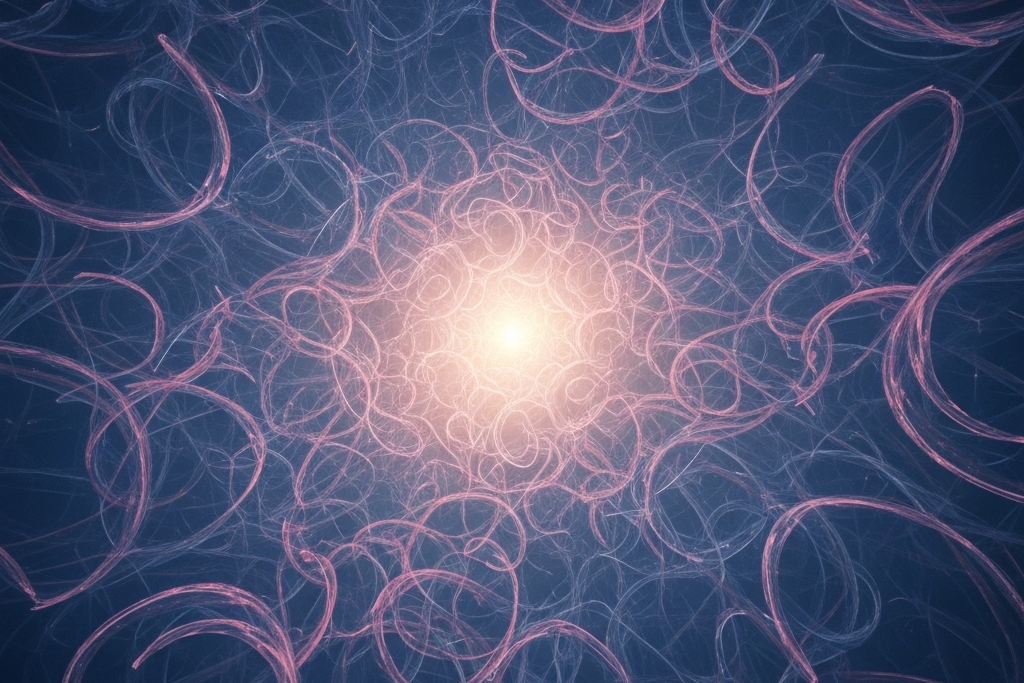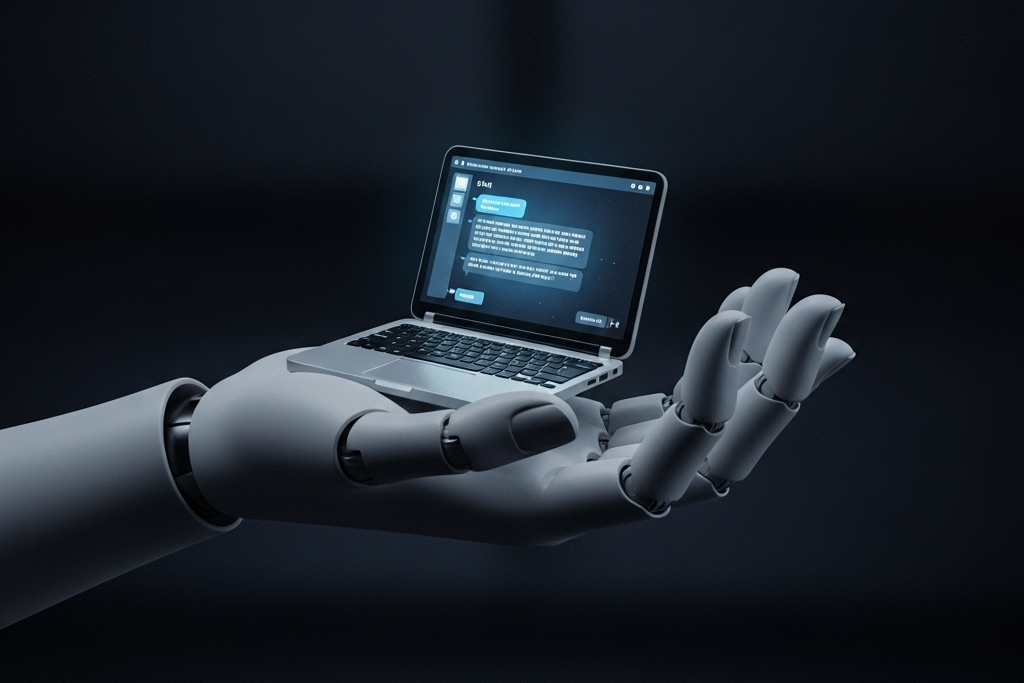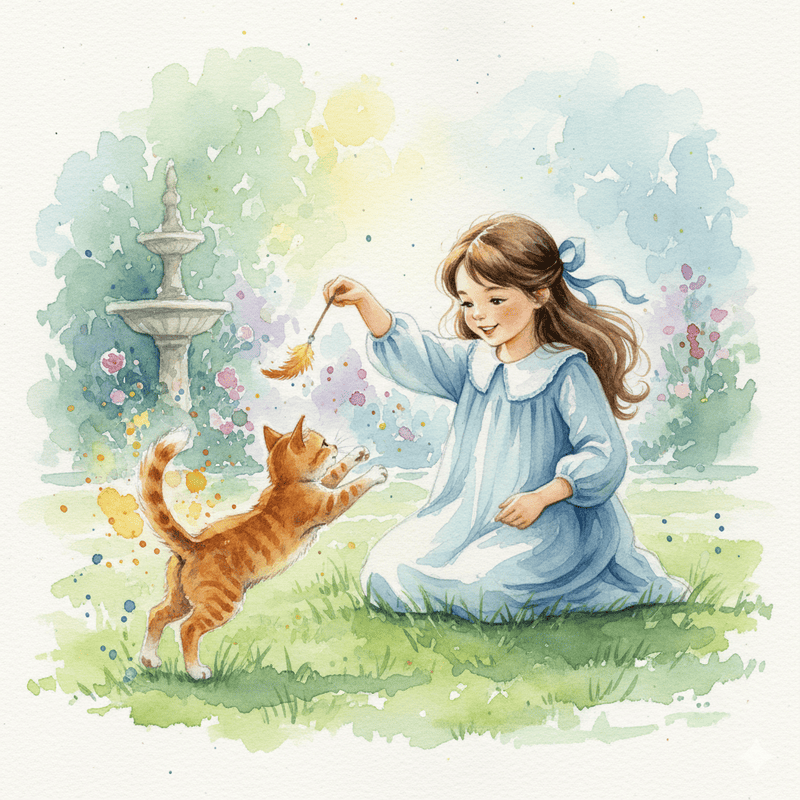-

アドラー心理学における『共同体感覚(Gemeinschaftsgefühl)』とは?
「共同体感覚」とは、アドラー心理学の中心的な考え方です。人は他者とのつながりの中でこそ、自分の価値を感じ、安心して生きることができます。アドラーは、他者を仲間として信頼し、自分も社会に貢献していると感じることが、幸福の本質であると説きま... -

【保存版】生成AIで作れる画像ジャンルまとめ|プロンプト付きサンプル一覧
生成AIの登場によって、誰でも簡単にリアルな写真や幻想的なイラストを作り出せる時代になりました。ChatGPTやGeminiなどのチャットAI(生成AI)にテキストで指示を与えるだけで、さまざまな画像を生成することができます。 生成AIは魔法のように画像を生... -

【まとめ】アドラー心理学に関する本
「人はなぜ生きづらさを感じるのか?」「どうすれば人間関係はもっと楽になるのか?」 そんな問いに向き合う中で、いつのまにかアドラー心理学に出会っていました。一時期はアドラー心理学に関する本ばかりを読み漁っていたような気がします。 この記事で... -

アドラー心理学に関する用語集
アドラー心理学は、オーストリアの心理学者アルフレッド・アドラーが提唱した「個人心理学」に基づき、人間を主体的で未来志向的な存在として捉える学問です。原因よりも目的を重視し、悩みの根源を対人関係に見いだす点が特徴です。 本記事では、その理解... -

嘘をつく脳、嘘をつくモデル――ハルシネーションの心理学
嘘をつく存在 「なぜ嘘をつくのか」という問いは、古来から人間を悩ませてきた。嘘とは欺くための意図的な行為なのか、それとも無自覚な誤りの延長なのか。近年、この問いは新しい文脈を獲得した。AIモデルが生成する「ハルシネーション」、すなわち自信た... -

失敗のデザイン――ハルシネーションを学習資源に変える賞罰の再設計
失敗はどこからやってくるのか 人は誰しも、できることなら失敗を避けて通りたいと願う。試験での誤答、仕事での見落とし、人間関係のすれ違い。 人生は細かい失敗で織り上げられているのに、私たちはその度に眉をひそめ、できれば「無かったこと」にした... -

正解より“ご褒美”――賞罰がハルシネーションを増やすとき
なぜ「正解」より「ご褒美」を欲するのか 学校のテストで、模範解答とは少し違うけれど「先生が好むであろう」表現を選んだことがある人は多いだろう。あるいは会議で、「真に効果的かどうか」よりも「上司が気に入りそうかどうか」を基準に発言を組み立て... -

仮想空間と「存在証明」――VR時代の「我思う、ゆえに我あり」
仮想空間で目を覚ます ヘッドセットを外すと、目の前にあるのは自分の部屋の天井。だがほんの数秒前まで、私はどこか別の都市の喧騒の中を歩いていた。耳に届くざわめきも、肌を撫でる風も、足元の石畳の感触さえもリアルで、そこに「いる」ことを疑わなか... -

生成AIに「◯◯として振る舞ってください」と頼むと精度が上がる理由とは?――最新プロンプトエンジニアリングとロールプレイの徹底解説
はじめに:AIに“人格”を与える時代がやってきた 生成AIに「経験豊富なコピーライターとして書いてください」と指示した途端、言葉遣いや文章構成がガラリと洗練される――そんなテクニックがあると聞いて初めて使ってみたときには、その出力の変化に驚きませ... -

AIプロジェクトを成功に導く「人工知能プロジェクトマネージャー試験」
「またAIプロジェクトが炎上している…」 あなたの周りで、そんな言葉を耳にしたことはありませんか? 期待だけが先行し、PoC(概念実証)の沼から抜け出せない。データサイエンティストと話が噛み合わず、要件定義が迷走する。従来の開発手法に固執した結...