「人はなぜ生きづらさを感じるのか?」
「どうすれば人間関係はもっと楽になるのか?」
そんな問いに向き合う中で、いつのまにかアドラー心理学に出会っていました。
一時期はアドラー心理学に関する本ばかりを読み漁っていたような気がします。
この記事では、私がこれまでに読んだアドラー心理学に関する本を紹介します。
アルフレッド・アドラー(著) 岸見一郎(翻訳)のシリーズ
著者の岸見一郎さんは哲学者で、アドラー心理学を紹介・翻訳し、教育や人間関係に応用して日本に広めた第一人者の一人とされています。著書『嫌われる勇気』で一躍有名になりました。
アルフレッド・アドラー(著)、岸見一郎(翻訳)のシリーズは、アドラー心理学を原典に近い形で学びたい人におすすめです。ただ、このシリーズの本はかなり難しい内容になっているので、何度も読み返す必要があり、チャレンジしたい人向けです。
人間知の心理学
自分や他人について知ること(人間知、Menschenkenntnis)は、誰もが関心を持つことである。
対人関係の悩みを解決するためには、人間知は不可欠であり、その知の内実は他者との関係から離れたものではない。
生き方・哲学に関心がある人、人間関係や教育・リーダーシップに悩んでいて考え方のヒントがほしい人におすすめです。2025年時点では新装版も発売されています。
人生の意味の心理学 上・下
われわれは現実を常にわれわれがそれに与える意味を通じて体験するのである。
つまり、現実をそれ自体として体験するのではなく、何か解釈されたものとして体験するのである。
私たちは必ず、自分の価値観や目的、過去の経験を通して「意味づけ」をしながら現実を体験しています。つまりアドラーは、「現実そのもの」ではなく「自分がどう意味づけするか」が人生を形づくる、と考えたのです。
こちらも、2025年時点では新装版も発売されています。
個人心理学講義 生きることの科学
人間が社会の中に住んでいるのは、個人が劣っており、弱いからである。
共同体感覚と社会的な協力は、それゆえ、個人を救済するものなのである。
アドラー心理学(個人心理学)では 「劣等感」 が中心的なテーマになります。
「もっとできるようになりたい」と感じるからこそ、人は努力し、学び、成長していきます。劣等感は成功や向上の出発点になります。しかし、劣等感に押しつぶされて「どうせ無理だ」と思ったり、他人を見下して補おうとしたりすると、心理的な問題や人間関係のトラブルにつながってしまうのです。
勇気はいかに回復されるのか
人生の課題に立ち向かうためには勇気が必要である。
人は「自分には価値がある」と思えるときにだけ、困難に立ち向かう勇気を持つことができます。人生の課題を避けるのは、それが困難だからではなく、自分に価値がないと思ってしまうからなのです。また、他者の期待に応えようと無理に自分を飾っても意味はなく、ありのままの自分を受け入れたときにこそ、本当の変化が始まるのかもしれません。
人はなぜ神経症になるのか
神経症者に「もしも私があなたをすぐに治したら何をしますか」とたずねたら、
神経症者が何を回避しようとしているかがわかる。
「この症状が出るようになってからできなくなったことはありますか」とたずねてもよい。
アドラーにとって神経症状(不安、強迫、うつ的気分など)は「逃げるための口実」であり、その人が意識的・無意識的に選んだ手段です。「過去のトラウマがあるから神経症になる」のではなく、「課題に立ち向かう勇気が持てないから、症状を選ぶ」という見方をします。
アドラー心理学では「すべての悩みは対人関係の悩みである」とされます。神経症も例外ではなく、仕事での人間関係、家族や恋人との関わりなど、他者との関係を避けるために症状があらわれると考えます。
神経症は「怠け」や「弱さ」とは違い、人生の課題を回避するための手段としての症状であるから、勇気づけによって解決可能であるということです。
ルドルフ・ドライカース(著) 宮野栄(翻訳) 野田俊作(監訳)
ルドルフ・ドライカースは、アドラーの弟子として、その思想を整理・発展させ、特に子どもの教育や家庭での実践に結びつけた人物です。彼のおかげで、アドラー心理学は世界に広まったと言われています。
アドラー心理学の基礎
アルフレッド・アドラーによる序文、アメリカ版への序文(R・ドライカースによる)、再販によせて(エヴァ・ドライカース・ファーガソン R・ドライカースの娘による)、日本版によせて(野田俊作による)を読める、アドラーファンにとっては非常に贅沢な一冊です。アドラー心理学を後世に伝える熱い意思が伝わってきます。
野田俊作(著) アドラー心理学を語るシリーズ
著者の野田俊作さんは、日本におけるアドラー心理学の第一人者の一人で、日本におけるアドラー心理学は野田俊作から始まったと言われているほどの重要人物です。
野田俊作さんの「アドラー心理学」に触れると、日本におけるアドラー心理学ブームで広まった「アドラー心理学」とは異なる印象を受けることでしょう。正統のアドラー心理学(思想ありきのアドラー心理学)、ここにありという感じです。
専門的な心理学書というより、日常生活に役立つ「生き方の本」になっています。野田俊作さんの語り口で、難しい理論も身近な言葉で説明されているため、アドラー心理学を語るシリーズは初心者でも安心して読めます。
エリート養成をやめるわけにはいかない。
私のもとで特訓を受けた人が、将来の指導者となって、アドラー心理学を導いていくことになると信じている。
私の課題は、私の生徒によい教育をほどこすことであって、私に考えられるかぎりもっともよい方法で後進を育成しているので、かならずその中から将来の指導者が育つと信じている。全員がアドラー心理学の供給者にならなくてもいい。
ソフトに面白くアドラー心理学を学んで、それでご自分たちの生活に役立つなら、それはそれできわめて結構なことだと思う。そういうことが、アドラーやドライカースが本来望んでいたことだ。
野田俊作:補正項より
性格は変えられる(アドラー心理学を語る1)
「自分の性格は生まれつきだから仕方ない」と思いがちですが、アドラー心理学では「性格は人生の目的に合わせてつくられたものだから、変えることもできる」と考えます。性格は、過去や遺伝に縛られるものではなく、自分の生き方の選び方から生まれるものです。
グループと瞑想(アドラー心理学を語る2)
何かを期待してグループに来ると、その期待が最大の障害になる可能性の方が大きい。
私のグループに来て、何かを学ぼうだの、成長して帰ろうだの、具体的な問題を解決して帰ろうだのというのは、とんでもない心得違いだ(笑)。
シリーズ第2巻は、グループ療法と瞑想について書かれています。「グループ療法」「瞑想」といった言葉が登場するので、びっくりするかもしれませんが、これが野田俊作さんのアドラー心理学です。
劣等感と人間関係(アドラー心理学を語る3)
シリーズの第3巻は、アドラー心理学の核心テーマともいえる 「劣等感」 と 「人間関係」 を扱っています。
「自分は他の人より劣っているのでは」と感じる気持ちは誰にでもありますが、それをどう扱うかで人生は大きく変わります。本書では、劣等感に押しつぶされず、それを成長の力に変えていくための実践的なヒントが語られます。
勇気づけの方法(アドラー心理学を語る4)
シリーズ最終巻のテーマは、アドラー心理学の実践の核心である 「勇気づけ」 です。
アドラー心理学では、人の不適応や問題行動の根本原因は「勇気を失っていること」にあると考えます。
他人に認められることに頼るのではなく、自分で自分を勇気づけられる人が、本当の意味で自立した人になります。自分で立つことができる人だけが、相手に依存せず、また相手を支配せずに、対等で協力的な関係を築けます。これが「真の共同体感覚」につながります。
日本のアドラー心理学ブームの火付け役
嫌われる勇気
アドラー心理学をわかりやすく物語形式で解説したベストセラー本です。
「青年」と「哲人」の対話によって進む構成になっていて、読者は青年の疑問を通して自然にアドラーの思想を学べるようになっています。
アドラー心理学をまったく知らなかった人にとっては、「トラウマは存在しない」「すべての悩みは対人関係の悩みである」「課題の分離」「共同体感覚」など、はじめて目にする言葉が多く、衝撃を受けた人が多いと思います。
人に嫌われまいと八方美人を続けて、気づけばすっかり疲れてしまった。そんなときは「嫌われる」という小さな代償を払ってでも、人間関係の重荷をおろして少し肩の力を抜いてみよう――。コミュニケーションがますます重要であると叫ばれている世の中にあって、「嫌われる勇気」というタイトルで世の中に投げかけたのは、お見事としか言いようがありません。
幸せになる勇気
『嫌われる勇気』の続編で、前作と同じく「青年」と「哲人」の対話によって進む構成になっています。本書は「アドラー心理学をどう実生活に生かすか」という実践的なテーマが中心で、特に 教育・愛・他者との関係 が深く掘り下げられています。
岸見一郎(著)
著者の岸見一郎さんは、日本でアドラー心理学を広めたことでよく知られている、日本におけるアドラー心理学の第一人者の一人です。岸見さんの語り口は穏やかで、難しい心理学や哲学の話もやさしい日本語に置き換えて伝えてくれるところに魅力を感じます。
アドラーを読む〈新装版〉: 共同体感覚の諸相
アドラー心理学の核心概念である「共同体感覚」を丁寧に解説する一冊です。
ドイツ語の「Gemeinschaftsgefühl」が英訳で「social interest(他者への関心)」とされた背景についての記述や、教育とは自己中心的な関心を他者へと向ける営みであるという説明などは非常にわかりやすいです。著者は、他者を認め、関心を持つことこそが共同体感覚の核心であり、幸福に生きるための尺度になるとわかりやすく語っています。
幸福の条件 アドラーとギリシア哲学
ソクラテスやアリストテレスが語った「善き生」と、アドラーの「勇気づけ」や「他者への関心」をつなぎ合わせ、幸福とは何かを哲学的に問い直す本で、日常に役立つ知恵が詰まっています。
愛とためらいの哲学
『愛とためらいの哲学』は、アドラー心理学の視点から「愛とは何か」を問い直す一冊です。幸福は対人関係の中で得られるとし、恋愛や結婚がなぜ難しいのかを哲学的に掘り下げます。問題は「誰を愛するか」ではなく「どのように愛するか」という姿勢にあり、愛は技術であると著者は語ります。相手に愛されようとして自分を変えるのではなく、自分も相手も尊重し、二人の課題として協力していくことが大切であると説き、恋愛に悩む人への道しるべを与えてくれます。
アドラーをじっくり読む
他人のせいにせず、自分を見つめ、生き方を変えることは厳しいものである
『嫌われる勇気』で一般的に広く知られるようになった著者が、アドラー心理学を原典から徹底的に解説する読書案内です。ベストセラー以降に広がったアドラー心理学に関する数々の誤解を正し、アドラー自身の著作に立ち返って思想の本質を示そうとしています。『個人心理学講義』や『人生の意味の心理学』など代表作をダイジェストで紹介しつつ、劣等感、共同体感覚、教育や愛といったテーマで丁寧に解説されています。心理学としてだけでなく、生き方を照らす思想としてアドラーを深く理解するための一冊です。
アドラー心理学 実践入門
アドラー心理学を日常に生かすための実践的な手引きです。「どうすれば幸福に生きられるか」アドラー心理学にもとづいて考察されており、「自分を好きになれない」「人の目が気になる」「他人とうまく付き合えない」といった悩みで重くなった心を軽くしてくれます。
子どもをのばすアドラーの言葉
「悪い親」がいるのではない、「下手な親」がいるのだ
アドラー心理学を土台に、親と子どもの関わり方をわかりやすく説いた一冊です。子どもを理想像に当てはめるのではなく、「ありのまま」を認め、尊敬し、成長を支える姿勢の大切さが書かれています。親の期待のためでなく、自分自身の人生を生きる勇気を子どもに与えることが、最大の支援であると強調。親子の諍いにとらわれず、かけがえのない存在として向き合う覚悟を促す実践的なメッセージに満ちています。
星一郎(著)
著者の星一郎さんは、日本でアドラー心理学を研究し、広める活動を続けてきた心理学者で、日本のアドラー心理学の第一人者の一人です。教育分野、子育てに関する本を多く出版されています。
アドラー博士の小学生に自信をつける30の知恵
皮肉にも、子どもに失敗させないようにと育てることが、最大の失敗になるのです。
子どもの「ほんとうの自信」を育てるための具体的な言葉と関わり方をまとめた実践書です。結果や欠点にとらわれず、努力の過程や「生きていること自体の価値」を認める視点を大切にし、子どもが自分をまるごと好きになるための方法が書かれています。親が発する何気ない言葉は、子どもの心を追いつめも育てもする「ことばの魔法」であり、親自身が自分を受け入れることの大切さも強調されています。
アドラー心理学で「子どものやる気」を引き出す本
子どもが自分に自信をもてさえすれば、すべての問題が解決する。
子どもは、自分が人のために何ができるかわかれば、自分に自信をもつこともできるし、自分を好きにもなれるのです。
子どもが自分を好きになり、自信をもつことで困難に立ち向かう力を育む方法を示した実践的な内容の本です。自己尊敬(セルフ・エスティーム)を土台に、比較や競争ではなく「人の役に立つ喜び」を感じられる関わり方が解説されています。結果より努力の過程を認め、現実の自分を受け入れる姿勢を育てることを重視し、親自身が罪悪感から自由になり、子どもの存在を尊重することが、やる気と成長を引き出す第一歩なのです。
マンガ・コミックでわかる系
本格的な解説書や実用書だけでなく、マンガやコミックも多く発売されています。難しそうに思える「劣等感」「課題の分離」「共同体感覚」といった考え方も、マンガなら登場人物のやりとりやストーリーの展開を追いながら自然に理解できますね。
アドラーの教え『人生の意味の心理学』を読む
人は「ありがとう」という言葉を聞いたとき、自らが他者に貢献できたことを知るのです。
アドラー心理学のエッセンスを漫画でわかりやすく解説した入門書です。「自己受容」「他者貢献」「他者信頼」の三点が共同体感覚を育まれるための条件。普通である勇気を持ち、ありのままの自分を受け入れることが出発点となり、他者とのつながりを通じて自己価値を実感できるプロセスを、親しみやすいストーリーで学べる一冊です。
コミックでわかるアドラー心理学
どんな人のどんなあり方も、ただ幸せを求めて成長した姿にすぎない。
誰でも必死にその環境で認められようとしているだけ。
アドラー心理学の基礎を物語形式で親しみやすく学べる入門書です。人は「目的」を持って行動するという目的論を軸に、全体論・社会統合論・仮想論・主体性といった重要概念を解説。意識と無意識は矛盾せず同じ方向に進むこと、誰も「なりたくて」困難な生き方を選ぶわけではないことを示し、正しく関心を向けられることで人は変われると説きます。自分や他者の存在を社会の中でどう位置づけるかを、漫画を通して理解できる一冊です。
マンガでやさしくわかるアドラー心理学
人間のあらゆる行動は、相手役が存在する対人関係である。
アドラー心理学の基本理論をわかりやすいストーリーと図解で解説する入門書です。人は過去や環境の犠牲者ではなく、自らの解釈と選択で未来をつくるという「自己決定性」や「目的論」を中心に、全体論・認知論・対人関係論といった重要概念を紹介。原因を探るよりも、未来を見据えて「勇気づけ」によって困難を克服する実践的アプローチを学べます。日常の誤った思い込みや「勇気くじき」に気づき、自分らしく生きる力を育む一冊です。
マンガでやさしくわかるアドラー心理学2 実践編
共同体感覚の訓練のスタートは「私」に対するこだわりを離れて、「仲間」を考えることです。
アドラー心理学の理論を学んだあとで、「どう活かすか」に焦点を当てた実践的入門書です。アドラー心理学を「活かす」ための発想として、「自己決定性発想」「建設的発想」「目的発想」「使用の心理学発想」「つながりと絆の感覚発想」「相互尊敬・相互信頼発想」「勇気づけ発想」の7つが紹介されています。
マンガでやさしくわかるアドラー心理学 人間関係編
多くの人は、相手を変えようとして空しい努力をしています。
アドラー心理学を人間関係の具体的課題に即して解説した実践的指南書です。著者が30年以上にわたり6,000人以上のクライアントと向き合った経験をもとに、人間関係を健全にするための方法を教えてくれます。人生における課題=ライフタスクにどう取り組むかが心の健康を決めると説き、相手を変えるのではなく「自分」「関係」「環境」から変えていく発想を重視します。人間関係に悩む人に勇気と実践のヒントを与える一冊です。
まんがで身につく アドラー明日を変える心理学
人は劣等感を何かで穴埋めしようとします。
同じ土俵で勝てないなら他の分野で勝とうとします。
つまり、劣等感を優越感で補おうとするのです。
劣等感や人間関係の悩みをアドラー心理学の視点から解きほぐし、日常に活かすための実践書です。劣等感は主観的であり、しばしば優越感で補おうとする心理を解説し、「課題の分離」によって自分と他者の責任を明確にする重要性が示されています。また、非難を避ける「Iメッセージ」や、自分の不完全さを受け入れて挑戦につなげる「不完全である勇気」など、実生活に直結する技法も紹介されています。
マンガでわかる!対人関係の心理学
人間関係の悩みを心理学の視点から解説し、具体的な改善法を提示する入門書です。他人の評価を気にしすぎる「対人認知欲求」や、自分を抑えて相手に合わせる「屈辱的同調」、思い込みによる「認知の歪み」など、関係をこじらせる要因を取り上げます。そのうえで、相手を変えようとするのではなく、自分の認知や行動を変えることが人間関係改善の第一歩であると強調されています。マンガ形式でわかりやすく、日常生活に役立つヒントが満載の一冊です。
実用・自己啓発・ビジネス
もっと気楽に読める実用書や自己啓発書、ビジネス書もあります。人間関係の悩みを解決するヒントや、チームで成果を出すための考え方など、アドラー心理学に関する本から学べることは尽きません。




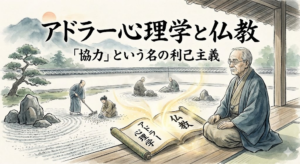
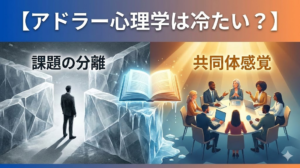



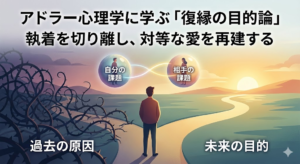
コメント